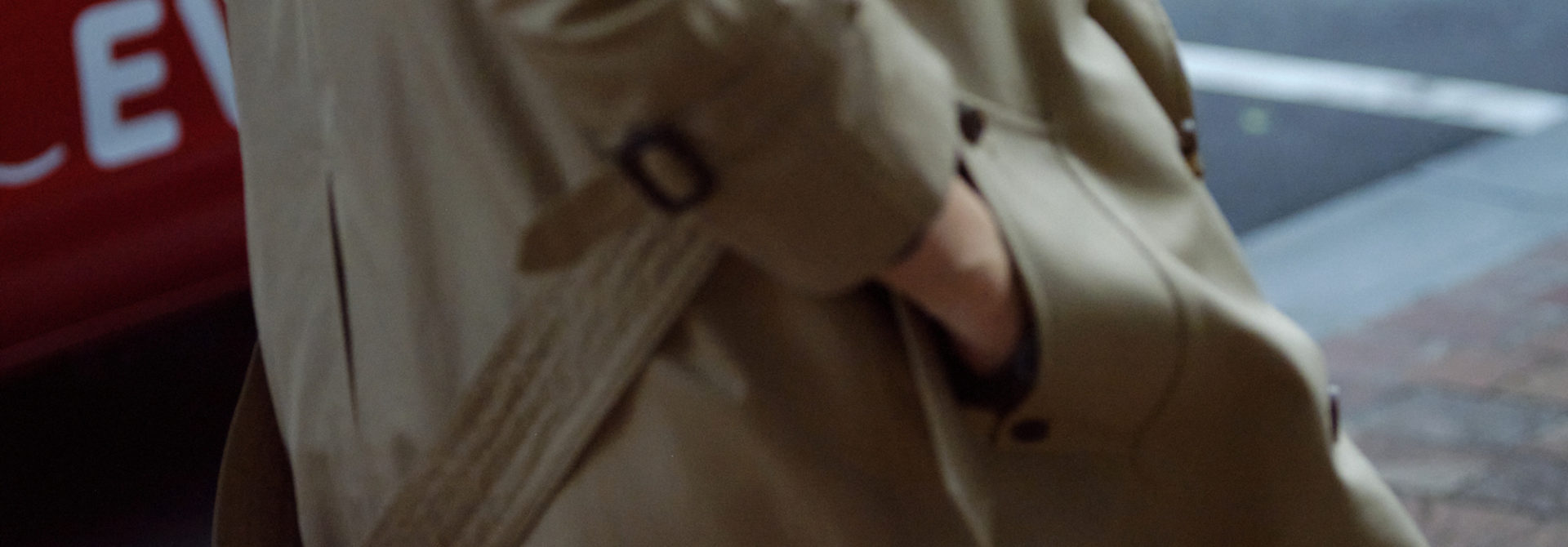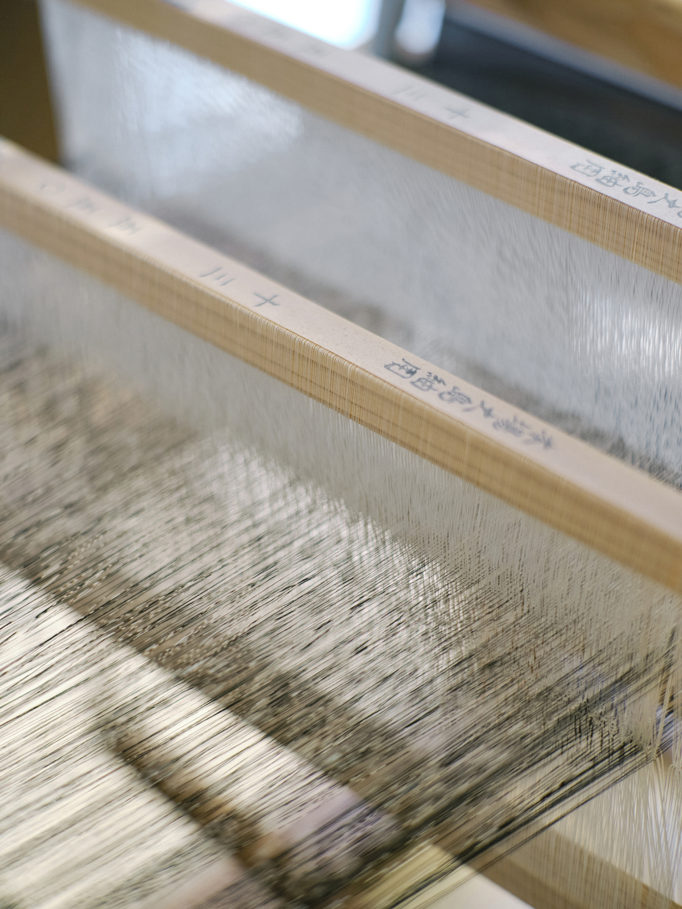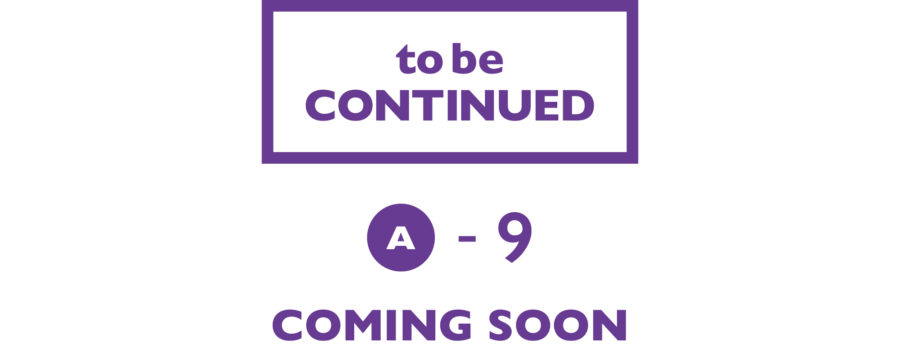Q: ご自身のインスタグラムでは、いつもカッコ良く和服を着こなしていますが、トレンチコートを着られることはありますか?
洋服も大好きなので、その日の予定に合わせて着るものを選んでいます。秋元 剛くんのインタビューを拝見したら、トレンチコートだけで10着以上も持っていると書いてあって、「さすが剛くんだな」って関心していたんですが、僕も数えてみたら10着以上ありました(笑)。昔からトレンチコートが大好きで、いつの間にか増えていたみたいです。それこそ、初めてトレンチコートをカッコ良いと思ったのはロンドンに住んでいた時です。当時はロックバンドのザ・リバティーンズが全盛期で、僕も一番好きなバンドだったんですが、ボーカルのピート・ドハーティや、ギターのカール・バラーがトレンチコートを愛用していて、ものすごく憧れました。ピートは僕の家の隣のバスストップに住んでいたらしく、普段から近所で見かけることも多かったんです。この前久々にピートの映像を見たら、見る影もなくふくよかな姿になっていてかなりショッキングでした(笑)。
Q: 泉二さんもロンドンではそういったスタイルでトレンチコートを愛用されていたんですか?
当時はまだ18歳か19歳ぐらいだったので、まだコート自体に馴染みがなくて、古着屋さんなんかで試着してみても、なんとなくしっくりこないイメージがあったんです。やっぱりトレンチコートは大人のアイテムっていう意識はあったと思います。当時はイーストと呼ばれるロンドン東部が盛り上がり始めた時で、週末になるといつもブリックレーンのマーケットで古着を漁っていました。トレンチコートに、バンドT、スキニーパンツ、ハット、シルクスカーフみたいな、それこそザ・リバティーンズみたいなスタイルが流行っていたから、僕も真似したかったんですけどね。
Q: そもそも着物専門店の二代目として生まれた泉二さんですが、どのような経緯でロンドンに留学されたんですか?
子供の頃から行事があるごとに着物を強制的に着せられてきましたし、父親も365日着物を着ていますから、ほかの家と違う和風の生活スタイルが嫌で嫌で。5歳ぐらいから着物を着ることを拒否するようになって、なるべく和風のスタイルから離れたいと思うようになりました。そして高校生になって将来何をやるのかを考えた時に、通っていた学校が男子校だったし、僕も周りも、ものの価値観が女の子にモテるかモテないかだけなんです。だから、ファッションに関わる仕事がしたいと思って留学という道を選びました。
Q: 留学先にロンドンを選ばれた理由は?
高校生の時は裏原ブームの真っ只中だったので、僕も裏原カルチャーにはかなり影響を受けました。その流れでスケボーにもハマっていたので、夜中になるとお店の前に三角コーンを並べて、ひたすらトリックの練習をやったりもしていました。銀座の真ん中でやることじゃないですけどね(笑)。でもだんだんダボついたストリートの服に違和感を感じるようになって、ヨーロッパっぽいスタイルに惹かれるようになりました。だから次第に遊ぶエリアも裏原から代官山に移っていき、聴く音楽もアメリカのグリーン・デイからイギリスのオアシスやザ・リバティーンズへと変わっていきました。そのあたりからイギリスのカルチャーがすごく好きになって、ファッションを学ぶならロンドンで学びたいと、自然と考えるようになりました。
Q: 大嫌いだった着物文化に興味を持ち始めたのはいつ頃だったんですか?
18歳になるまで当たり前のように日本で暮らしてきましたが、やっぱり日本から出て、知らない国で外国人として暮らすようになると、差別を受けることもありますし、日本のことを聞かれたりもしますし、自分が日本人だっていうことを強く意識するようになったんです。そんななかで、ロンドンではロンドン・カレッジ・オブ・ファッションという学校に通っていたんですが、その授業でヴィクトリア&アルバート博物館に行った時に、民族衣装に関する課題が出たんです。各自ひとつの民族衣装を選んで課題を制作するんですが、クラスメイトの多くが和服を選んでいたんです。お洒落な友達も着物に対してすごく興味を持っている様子を見て、そこで初めて「着物ってカッコ良いんだ」ということを実感しました。父が着物屋をやっているっていう話はみんな知っているから、僕にいろいろと聞いてくるんですが、正直当時は着物のことを何も知らなくて、着物と浴衣の違いすらわからない状態だったんです(笑)。
Q: 留学したことによって、ご家業や父親に対する意識はどのように変わりましたか?
自分たちの文化に興味を持ってくれている人たちに、きちんと伝えていくことはすごく大事だなって思うようになりました。その点に関しては、留学してから自分のなかで大きく考え方が変わったと思います。今も強烈に覚えているのは、僕がミラノに遊びに行った時に、出張中の父と現地で落ち合った時のこと。父とはミラノの中心地にあるドゥオーモ(ミラノ大聖堂)で待ち合わせることになったんですが、そうしたら案の定、父はバリバリの着物姿で現れたんです。その時僕は21歳で、子供の頃からあれほど嫌だった父親の着物姿が、なぜだかものすごくカッコ良く見えたんです。そこから、いつか自分も着物を着てみたいと思うようになって、将来的に家業を継ぐことを意識し始めました。
Q: ロンドンの学校を卒業されてから、どのような仕事に就かれたんですか?
卒業後はロンドンのいくつかのセレクトショップでバイト後、パリにも1年間滞在し、日本に帰国しました。その後日本のブランドに就職が決まったタイミングで、突然父親が体調を崩したんです。将来的には銀座もとじで働こうと考えてはいましたが、どうせやるのであれば、始めるのは早いほうが良いと思い、決まっていた就職先にはお断りをして、25歳の時に銀座もとじで働くことを決めました。
Q: 25歳で突然着物の世界に飛び込んで、戸惑いはありませんでしたか?
とにかく着物を着たこともなければ、着物のことを何ひとつ知らなかったので、最初の数年は本当に大変でした。着物の上に着る道行(みちゆき)コートを指差しながら、「この“どうこう”コートって何ですか?」と質問する僕の姿を見て、僕と同期の同僚は、「呉服屋の息子が“どうこう”って言ってる!」って驚愕したみたいです。その後、朝日新聞の取材を受けた時にその話をしたようで、僕の恥ずかしいエピソードが一面で紹介されてしまいました(笑)。
Q: 今では着物姿も板についていますが、着物を着て過ごすことにはすぐに慣れましたか?
着物を着始めた3日目で、お客様に「あなたはもう着物を着るのはやめなさい、全然似合わない」って言われちゃいました。でも、着物屋で着物を着ないのはありえないと思って、ずっと頑なに着続けたんです。数年経ってからようやく、そのお客さんから「だんだん板についてきたわね」って言ってもらえるようになりました。それは本当に嬉しかったですね。
洋服に着替えて銀座の街を散策している泉二さんの足は、自然と行きつけのバー・居酒屋 あるぷへと向かっていた。「狭い路地の奥にある怪しい店舗の外観に尻込みしますが、実際は居酒屋のようにフラっと立ち寄れるクラシックなバーで、タイムスリップしたようなレトロな内装も最高ですよ」
Q: 銀座もとじでは「男のきもの」という男性向けの専門店を展開していますが、着物の業界において男性向けの取り組みは珍しいのでは?
「男のきもの」は父が2002年に立ち上げたのですが、おっしゃる通り、呉服業界では男性専門店というのは非常に珍しいものだと思います。そもそも銀座もとじは、昭和50年代を境に呉服産業全体が収縮しているなかで、奄美大島から上京した父親が、銀座の地でゼロから立ち上げたお店です。数百年続くような老舗が多い業界のなかで、それは普通に考えると無謀なチャレンジだと思われるでしょう。父はよく「業界の常識は一般の非常識」という言葉を使うのですが、誰もやっていないことに目をつけて、独自の手法で道を切り拓いていくような父の反骨精神やチャレンジ精神は、簡単に真似のできるものではないと思います。実際に「男のきもの」を始めた当初は、周りから「あそこはすぐに潰れる」と言われたことも多かったみたいです。でもそういう新しい試みが評価されたのか、今では顧客の4割を男性が占めるまでに規模が拡大しています。
Q: とはいえ、着物文化や和風の文化に触れたことのない世代が増え続けている今、男性向けの着物というニッチなビジネスに明るい未来はあるのでしょうか?
男性の着物には、可能性しかないと思っています。着付けの修練が必要な女性の着物とは違って、男性の着物は、着るのが簡単なんです。それこそネクタイを締めるような感覚で着られますし、着心地も堅苦しさはありません。しかも、男性は素材や製法や作家性に対するこだわりも強いですから、一度深掘りしだすと、ものすごく深いところまで追求していきます。銀座もとじにも世界的なファッションデザイナーの方々にたくさん来ていただいていますが、ファッション感度の高い方々は、着物文化を通して、日本のエクスクルーシブなラグジュアリーを存分に楽しんでいます。
Q: 泉二さんはインスタグラムやYouTubeなどはもちろん、テレビや雑誌などのメディアでの情報発信にも力を入れているようですが、そういった活動の必要性はどのようにとらえていますか?
僕たちが扱っているものの裏側には、必ず物語があります。だからうちの店では、自分たちが目で見て、耳で聴いて、手で触って、心で感じたものを、自分たちの言葉で伝えるということをモットーにしています。でも、かつての僕のように、普通に生活していると、着物や日本の伝統文化に触れる機会はなかなかないと思うので、そういうものとの接点となる情報発信のチャンネルと、誰かの興味に引っかかるフックはなるべく多いほうが良いと思っています。将来的には、着物に関わる仕事を人々から憧れられる職業にしたいし、着物をワードローブのひとつの選択肢として定着させるという目標もあります。それこそお金が貯まった時に、車を買うのか、時計を買うのか、ジュエリーを買うのか、そのなかのオプションとして、着物が入ってくるような時代が来ることを願っています。

銀座もとじ店主
泉二啓太
もとじ・けいた 1984年東京都生まれ。高校卒業後に渡英、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションにてファッションを学ぶ。その後パリへと渡り、6年間の海外生活を経て、2008年に帰国。’09年に株式会社 銀座もとじへ入社。取締役専務を経て、’22年9月に父親の跡を継いで代表取締役社長に就任。男の着物専門店・銀座もとじ「男のきもの」のオリジナル商品の企画から開発、ヴィジュアル制作までを統括する。Instagram @ginza_motoji, @keitamotoji