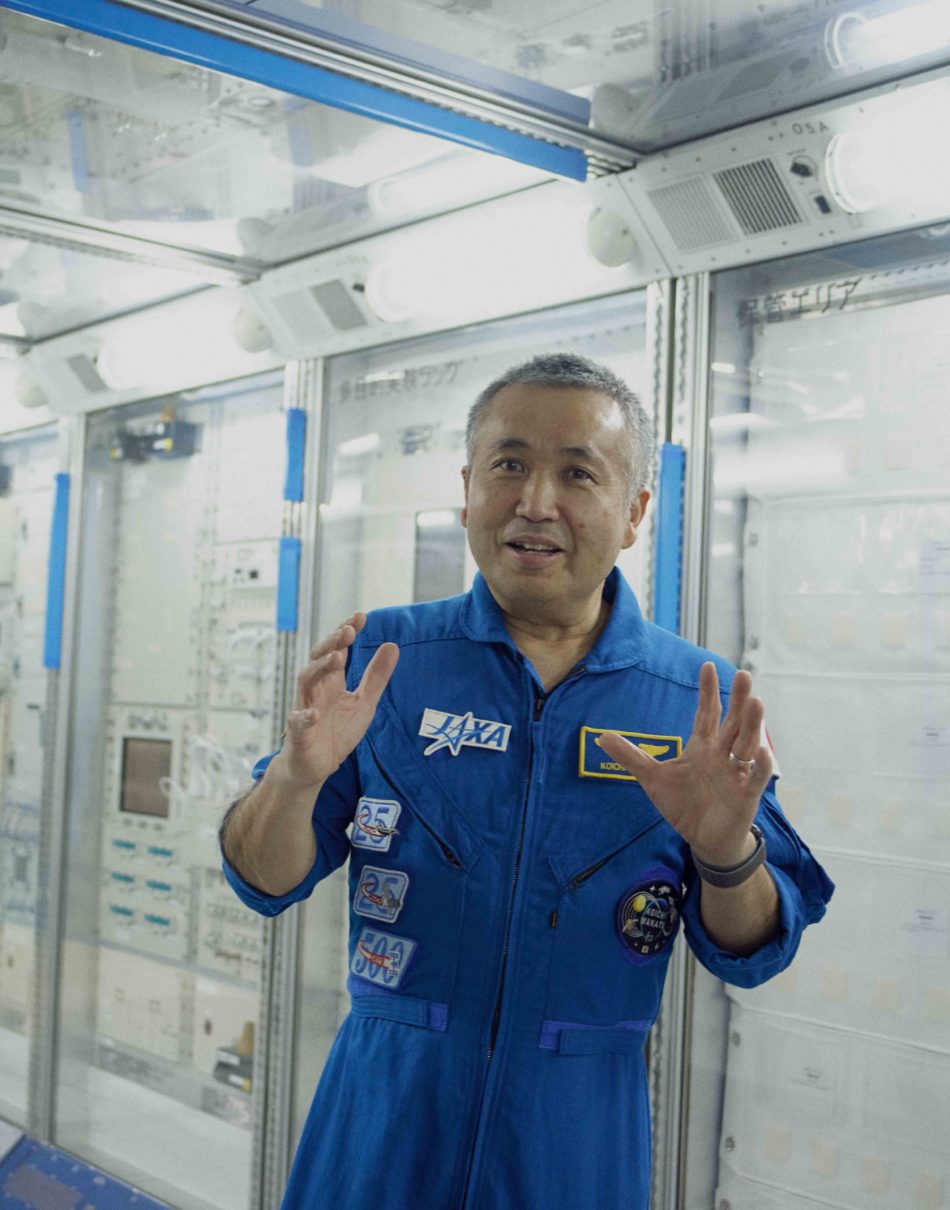自然に焦れた少女が、表現したかったこと
当たり前のように都心で暮らしながら、『赤毛のアン』の世界に憧れてきた幼少期。すぐに靴を脱いでしまうような女の子は、徐々に自然の世界へと導かれていきました。会社勤めを経験したけれど、文句ばかりを言っている自分が嫌になってしまったという野村さん。「楽しい」と言っている自分に出会う為、動き出しました。料理人としてレストランを開業させながら映画も撮り、長寿となるラジオ番組を持ち、数多くのメディアにも出演していきます。
「当時、“ロハス”という言葉が流行っていて、私の活動のかんむりに全部“ロハス”という言葉がつくようになったんです。本音を言えば、そういうことに捕われず自由でいたかったんですねきっと。だから、嘘をつけない表現者を映し出したくて、映画『eatrip』を撮りました。それは、長生きすることも全部含め、“生きる”ということが私にとってのロハスだと表現したかったんです。その後で、私は単純に料理のことが好きだったことに気が付いて、カリフォルニア州のシェ・パニーズの厨房に入ったんです」
アリス・ウォータースのシェ・パニーズは、自然派レストランとしてその名を世界に知らしめる名店。毎日200人近いゲストが訪れ、振る舞われる料理はすべてオーガニック。地産地消でありながらサスティナブルを目指し、食の未来を考えた、美味しい革命を引き起こしました。
「食を扱うアート集団に触れて、自分のオアシスを見つけた! と思いました。アリスは、『シェ・パニーズの厨房は、オーケストラだから』と言うんです。それは、全員がそれぞれの個性で演奏していいということ。ちゃんとした指揮者がいれば、その日に最高の演奏ができるというレストランなんです。それは私の感覚ととても近かった。私も、社会との繋がりとなる“場”を常に探していたから」
「無」を知ることは、「自分」を知ること
そんな“場”を作り出したいと思った時、野村さんがまず発想したことは、「何もなかったら、人はどうやって生きて行くのか」ということでした。更地に木を植えて、畑を作ること。最低限の衣食住が自然物から生まれていくこと。そんな場所で、ちょっと料理をしたら人が立ち寄るだろう、花を生けるだろう、壁に絵を描くだろう••••••。そんなことを妄想しながら、自分のなかにある本当に必要なものを残していった時、野村さんが見つけたのは「大丈夫」という感覚でした。
「世界がものすごく進化していくと、自分では直せないものに囲まれてしまう不安があります。車が壊れても、携帯が壊れても、私は直せない。すごく不安で、どこか迷子になってしまう感覚があって。例えば、ガスが止まったら火を起せばいいというような、大丈夫、何とかすれば生きて行けるから、という感覚が欲しかったんですね。そういうことを疑似体験でもいいから、触れられる場所が必要だと思ったんです」
未来へと守り繋いでいきたいもの
そうやって“自分が自分にしてあげられること”を追求している野村さんの周りには、“良いこと”の連鎖が次々と生まれ、彼女の人生を作り出しているようです。生産者、畑、料理、建築、すべてが回りながらゆっくりと調和しながら動いています。それは同時に、過去のものを未来へと繋いでいくことでもあるのです。
「楽しい日常も美味しい食べものも消えてしまうものだけれど、すごく生きている感じがするし、記憶や感情として残ります。だからものを所有するならば、なるべく愛着を持っていたいですね。そして本当に大事なものならば、いつか大切な人にあげたくなります。そうすると、ものに温度が出てきて、例え持ち主が生きていなくても、そのものが生きていく感じがありますから」
そんな野村さんの目線の先には、古い木のデスクがありました。かつて祖父が使っていたというデスクは、釘が1本も使われていない為、分解して持ち運ぶこともできます。机のアコーディオンを閉めると、自動で引き出しの鍵が閉まるというカラクリには、野村さんも心底驚いたと言います。お母さんの同級生から譲り受けて大切に着ているブラウスも、新しい生地で縫った昔ながらの割烹着も、良いものはずっと繋がるということを、野村さんは信じています。好きだから大切にする。好きだから守る。好きだから伝える。“好き”という気持ちと、“楽しい”と感じること。とてもシンプルなそのふたつの感情を野村さんは、大切にしています。
循環を生み出す、言葉のちから
「まだ20代の時に出会ったどこか不良みたいなおじさんが、今70代になっていて、人生がすごく楽しいと言うんです。そのおじさんから、『神さまは誰にも教えてくれない』って言われました。その人が遅咲きだとか、未来に何が起こるかなんてわからないと。『人生は意外と長くて、これまでの知識が邪魔になることも多いから、自分が本当にやりたいことがあるのなら、それまでの経験は一度置いて、次の20年をかけてやりなさい』って。そんな大先輩の言葉も、私を循環させてくれるものなんですね」
野村さんの心を突いた74歳の言葉は、いつか彼女も、自分の人生と重ね誰かに伝えていきたいという。
「年配の人たちには辛辣なことも言われたりします。でも、良いことばかり言う人が寄り添ってもしょうがない。核家族が多いなか、世代を超えて親身になって寄り添える関係がない今は、その大事さを身に染みて感じます。私は次に、20代30代の若い人たちに何かを繋いでいきたいと思うんです。気が付くのがたとえ10年後だったとしても、その人にとって何が種になるかわからないから」
空へ空へと伸び競う植物たちの様子、大輪の花を咲かせた後に残る質朴で儚い種、手作りの温もりが残る調味料や農産物に、先人たちの声。食べることと同じくらい大切にしたいそんな循環の場では、誰もが一度立ち止まって、生きることの美しさを感じることができるのです。

料理人・restaurant eatrip主宰
野村友里
のむら・ゆり おもてなし教室を開く、母・野村紘子さんの影響を受けて料理の道に。2009年には初の監督作品『eatrip』を公開。その後、restaurant eatripをオープンし、パーティなどのケータリングフードの演出、雑誌の連載やテレビ、ラジオの出演、本の執筆などその活動は多岐に渡る。2020年1月にグランドオープンした表参道GYRE4階のGYRE.FOOD内にグローサリーショップ・eatrip soilを開業。“人生とは食べる旅”と、ライフスタイルとは切っても切り離せない食文化を、常に新しい視点で再解釈し、発信を続ける。Instagram @eatripjournal, @eatripsoil, @restaurant_eatrip